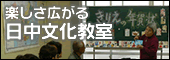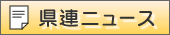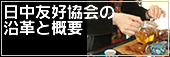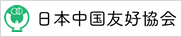![]()
− その他
内蒙古で過ごした少年時代(中)
内モンゴル「張北」の平原に立つ筆者
初夏、父に連れられ城外に出ると草原がどこまでも広がり、羊の群れが点在している。近くに寄ると数百頭の羊が草を食むのどかな風景があった。城外の近くには畑があり、そこに美しい紅白のけしの花が一面に咲いていた。花が散るとピンポン玉ぐらいの青い実がなった。中国の農民が青い実に傷をつけて、出てくる白い汁を小さい缶に受けていた。それが恐ろしい麻薬「アヘン」の原料であることを知ったのは、ずっと後のことである。
父が珍しくけしの花を詠んだうまくない歌がある。
城外に一歩いずれば ひろびろき 畠にけしの花のなみうつ
そして、注を書き付けている。「日本ではご禁制になっているから、けしの花はまったく見られないが、蒙古国では、重要な財源になっていたので、むしろ政府が奨励して作らしていたのである」と。
つまり、日本が支配する蒙彊政府は、中国農民にアヘンの原料であるけしの花の栽培を強制し、アヘンを作り,裏で中国人に売って精神的に堕落させ、経済的に大儲けしたのである。儲けた金は、満蒙の傀儡政府の財源や中国侵略の軍事費になったのである。
私は、日本と中国の歴史家の共同研究によって蒙彊政府の犯した罪が全面的に明らかになることを希望する。現地のアヘンにまつわる資料は、敗戦のとき軍と警察は焼却して退散したのだろう。二〇〇九年、私が張北を訪ねたとき、現地政府の応対した人の話では、ほとんど資料は残っていないとのことであった。
一九四五年八月、敗戦前後の記憶は鮮烈である。父は四二歳にもなっていたが、在郷軍人として召集され張北の駐屯部隊で、にわか仕立ての軍事訓練を受けた。四週間、わら人形を銃剣で刺す人殺しの訓練や銃の射撃の稽古の明け暮れであったという。母の方も幼い弟を背負い竹槍で人殺しの訓練であった。
新聞もラジオもない辺境の地であったが、八月六日,九日、広島と長崎の原爆投下のニュースは強烈な新型爆弾として程なく伝わってきた。ほとんど同時にソ連参戦を知った。ソ連軍は特に婦女子に対し奪略暴行するという風評が広がっており、日本人は恐れ混乱した。
八月十一日正午ごろ「ソ連軍の装甲車七十台が張北に向かっている」と知らせが入った。三時間後には張北は襲撃されるということであった。しかし、ずっと後にそれは流言飛語の一つであることがわかった。
母は炊きかけの飯を弁当につめ、非常食の乾パン、リュックサック三つと水筒を子供に持たせ、赤ん坊の弟を背負い、両手に幼い弟を連れ、前に袋をぶら下げた状態で家を出て集合場所である役所に向かった。袋の中身は、弁当と弟のおしめ、祖父母の位牌、救急薬の代わりのもぐさと線香であった。そのとき私は10歳、下に弟妹5人いた。
父は守備隊として留め置かれた。混乱の極である。父との別れに当たり、必ずしも再会を期しがたかったが、父は再会を約し母に死ぬなと言い渡した。トラックにぎゅうぎゅうに詰め込まれ、危険の中、野を越え、山を越え万里の長城の外側から内側の張家口にたどり着いた。避難所(どこかの宿舎)は避難民で溢れていた。大日本帝国崩壊の瞬間である。
おかげで父は戦死せずにすみ、そこで家族一緒になれた。それまで威張って街を闊歩していた日本人は、中国人の報復を恐れ家から一歩も出歩けなくなった。八月十五日の敗戦の日を過ぎてからも、ソ連の軍用機が銃撃し爆弾を落とした。近くで爆発した爆弾の小片が父の足に刺さった。
まもなく張家口も危ないとのことで天津を目指し避難民の大移動が始まった。苦難の逃避行の始まりである。何十台かのトラックは、子どもや年寄りをつぶれんばかりに乗せ次から次に名も知らぬ駅まで運んだ。泣き叫び怒号が飛び交う中で長い無蓋貨車に鈴なりのように詰め込まれた。父は列車を警備するため徴用され、家族と別行動であった。
(つづく)
鳥居 達生・県連副会長(1934年生まれ)