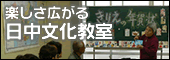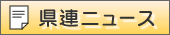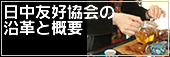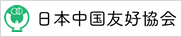![]()
− 中国の旅
中国東北部(旧満州)旅行記
体験語れなかった父の足跡をたずねて
長い間私にとっての中国は、未知なる恐怖の対象であった。
なぜなら父が日本兵として中国に渡り、語れないほどひどいことをしたということを、知っていたからだと思う。私は昭和28年に生まれたが、物心ついてから記憶の中にある父は絶えず「生き残った」ことを悔いる言葉を口にしていた。
しかし、「加害者」としての自分の行為は記憶の奥へ追いやってしまった。そしていまだに日本兵としての体験を誰にも語ることができないでいる。だから私は、すべての中国人は日本人を憎んでいると信じて疑わなかった。そんな私が中国と向き合おうと思ったのは、16年前、40歳をはるかに超えた時からである。
専門学校で社会福祉士養成に携わっている私は、日常生活に支援の必要な人(以下当事者)を理解する演習という授業の中で、「中国残留日本人」を取り上げている。そのきっかけは、名古屋で残留孤児裁判が行われていた時支援集会に参加したことだ。驚いたことに福祉関係者が一人もいなかった。
残留孤児が最も多く受けている福祉の支援は「生活保護」であったが、ケースワーカーの対応は「支援」という言葉とは程遠い労働の強制だったり、監視的であったりした。人間性にあふれた本当の「支援」を行っていたのは、早期に帰国した「知人」や「弁護士」、「ボランティア」だった。
その現実は、戦後最初の生活保護裁判として有名な「朝日訴訟」を思い起こさせた。
支援集会に参加して以来、私は授業で中国残留日本人を取り上げることにした。ある残留孤児は、日本語が話せないばかりでなく、学ぶ機会のなかった生活で文字が書けなかった。この人の日本での生活は、同じ日本人からの嫌がらせを受けながらの労働、低賃金による生活苦に満ちていた。
また、開拓団として入植し20歳で敗戦を迎え、家族を守るために中国人の花嫁になった残留婦人は、方正県での厳しい生活の話をしてくださった。
また、地域の9条の会で中国からの引揚体験を話してくださった人は、牡丹江の「酒保」(軍関係者が利用する百貨店のようなところ)で働く父とともに中国に渡り、引き揚げの途上で幼い弟と妹を失ったが、健康と年齢のせいで、もうそこに行くことはできないだろうと話された。
(つづく)

体験語れなかった父の足跡をたずねて
日本福祉大学中央福祉専門学校 永井淑子