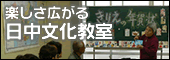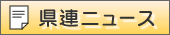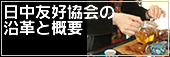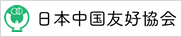![]()
− 講演・学習
8月11日(2023)山本講演「つくられた台湾有事ーーー」質問と回答
質問にお答いたします。
【質問1】「トゥキディデスの罠」に関連し、アリソン氏によれば、500年の歴史を紐解き、その間、新興国が覇権国の支配を脅かす緊張が16回あったがうち12回が戦争となり、戦争が回避されたのは4回だけであった、と米中戦争の危機を警告している、ということである。それでは戦争が回避されたその4回はなぜ回避されたのであろうか。
【回答1】;アリソン氏があげる、戦争を回避できた「4回」の対決とそれらから得られるヒントは次の通り。
⓵15C末、海上帝国ポルトガル対スペインの抬頭。
ヒント・高い権威の存在(教皇)が対立解決の助けに。
⓶1990年代〜現在;英・仏主導の欧州対東西ドイツの統合。
ヒント・国家より大きな機構に組み込む。
➂20C初め;米対英の覇権国交代
ヒント・賢い国家指導者を擁する(国益を犠牲にせずに要求に応ずる外交的スキル)
➃1960年代〜80年代:ソ連・東陣営対米国・西陣営の決定的対決
ヒント・米ソは前例のない核兵器の存在をベースに軍事力攻撃以外の全方位的な攻撃=競争を組織的、持続的に行った(冷戦構造)。併せて米ソは競争の周りに過熱を抑える複雑な仕組みを構築した。
質問への回答は以上となりますが、アリソン氏の主要テーマは「米中戦争前夜」という事実認識と警告、それを回避するための思考にあるので、改めて著書(邦訳)を紹介しておきます。グレアム・アリソン著、藤原朝子訳『米中戦争前夜』ダイヤモンド社、2017年。
加えて、船橋洋一氏(元朝日新聞主筆)の同書序文の言葉も紹介しておきます。「後戻りできない地点はどこかを先回りして確定し、そこから双方にとっての『レッドライン』を双方の指導者が確認しあい、それを踏み越えないようにすることが求められている」、これは至言ですね。
【質問2】野党といいますか、中国に関して言えば「日中友好議員連盟」という存在があり、公明党の議員なども参画している。岸田内閣が中国との対決姿勢を示しているとき、かれらの役割は期待できないのかどうか。
【回答2】;岸田内閣が国会に諮ることなく、絶対多数に安住した閣議決定で「安保三文書」(⓵中国による世界秩序への挑戦という脅威、⓶敵基地攻撃能力の確保、➂軍事予算のGDP比2倍化)を決めました。米国のシナリオを丸まま受け入れ、憲法の「専守防衛」原則を放棄し、安全保障政策の転換ともなる文書です。まさに野党だけでなく与党も交えた国民的議論が行われるべき問題です。
中国をないがしろにする枠組みですから、自民党の二階俊博議員が会長を務め、超党派で構成される議員連盟「日中友好議員連盟」は、この国民的議論の中心となってもおかしくありません。ところが、「親中」とも言われてきたご指摘の公明党は、この敵基地反撃能力の確保を含む「安保三文書」に対して、閣議決定前の自民・公明両党実務者協議で承認しているのです。
戦争に直結しかねない「安保三文書」を前に、国会内外での国民的議論も行えないという背筋が寒くなるような現状(「新しい戦前」)は、日本の政治の危機を表していると思います。自公連立による絶対多数の成立は改憲のベースであり、改憲の前提ともいうべき安全保障政策の本質的転換に公明党も賛成の立場に立ったわけですから、改めて憲法改悪を阻止するための草の根・地域ぐるみの国民運動の再構築が喫緊の課題となっているのです。
【質問3】19世紀初め、中国のGDPは世界最大の力をもっていたという表を示された。その際、第2次大戦後の米国は世界のトップとなったけれども、19世紀中国の地位には及ばなかったと言われたが、異和感をもった。19世紀初頭の世界と20世紀半ばの世界とは量、質とも異なるものではないだろうか。
【回答3】整理しておきましょう。世界各国の経済力は国民総生産(GDP)という量的規模で示され、各国の経済力を比較する場合は共通基準として米ドルに換算して比較されます。実質的な経済力比較としては、各国のGDP(ドル換算)を各国の人口数で割った「一人当たりGDP」が使われます。
さて、次の例を見ましょう。「00年に世界GDPの14%を占めていた日本は、20年には6%にまで落ち込んでいる。IT革命を主導したアメリカも、同期間に30%から25%に下がった。そして、日本を除くアジアの比率が7%から25%まで伸びている」。これは抵抗感なく納得できますね。2000年から2020年にかけて経済成長がどんどん低迷した日本、経済成長が鈍化した米国、この間経済成長で躍進した中国を含むアジアの姿がくっきりと浮かんできますね。ここでいう%は、世界のGDP合計額に対する各国のGDPの割合の消長を示しています。「⓶2020年の世界のGDP合計額」は、世界経済が成長していますから「⓵2000年の世界のGDP合計額」よりも当然大きいです。でも世界のGDPの合計額を%で表すと⓵も⓶も100と表されています。この場合の比較はあくまで数量的な比較です。
1820年の世界GDPの合計額は%では100であり、中国はその32.9%という圧倒的な割合を占めており、後の帝国主義となる先進地域は合計しても27.9%を占めるに過ぎなかったわけです。ところが1950年には中国のGDPは4.6%に落ち込んだのに対して、先進地域は59.9%に、とくに米国は単独で27.3%に躍進したわけです。世界のGDPは1820年から1950年にかけて何倍にもなっているでしょう。中国は何もせずに落ち込んだのではありません。香港、次いで台湾、さらに満州を植民地化され、中国全土を日中戦争で国土、資源、人口が荒廃させられた結果として惨憺たる転落を強いられたのです。ここから復興、建設、発展、競争をへて現代的先進国をめざすのですから、並大抵の覚悟・努力ではありません。
【質問4】日本総研会長の寺島実郎氏はよく日本の政治にはグランドデザインがないと指摘されている。外交にしても経済にしても、また当然日中関係を考えるにしても、まず日本はどうあるべきかというグランドデザインが必要なのではないだろうか。
【質問5】アメリカは火種のないところに台湾有事という火種を作り出している、それは確かに言える。しかし、それで中国に一時的なダメージを与えることができたとしても、日本などアジアの諸国が放置せず、アメリカに対して外交と対話の力で国際協調、平和構築に向かわせるべきだというのは正論だとしても、現実には戦後一貫してアメリカに追随してきた日本にその力があるとは思えないのだがどうか。
【回答4・5】;4と5とは同じメダルの表裏と申しますか、併せて考えて参りましょう。
日本総研寺島氏は日本の政権や政治家、財界そしておそらくメディアの間でも、グランドデザインが欠如したままの計画や政策の策定、発信、実行が行われがちであり、錯誤、混乱、意図せざる低迷に陥ることのなんと多いことかと、嘆かれてます。その鋭い批判的精神には私どもも自らのチェックを迫られることがあります。かれが心がける事実認識、歴史の検証、豊かな選択肢をもつ未来構想に支えられたグランドデザインの重要性については、しっかりと受け止めたいものです。
ここでは、まさに厳しさを増す米中対立の中で日本はどうあるべきか、その寺島氏の見識に耳を傾けてみましょう。「岸田首相は『自由で開かれたインド太平洋』という言葉を使っているが、そこには中国封じ込めの意図が見える。アメリカと連携しつつ政治的には中国を封じ込めることに軸を置きながら、経済政策においては中国やアジアとの依存関係を深めているところに日本の危うさがある。日本は米中対立に分断されることなく、真の意味での自立自尊を目指さなければならない。アジアと連携しながら国際社会の中で第三のスタンスをしっかり作れるかどうかが最大の課題」となっている〈寺島実郎、https://net.keizaikai.co.jp/62721 〉。
後者の質問5は、寺島さんや私が主張するような、米中対立のはざまにあって「自立自尊」、自立的思考に立って、「第三のスタンス」で戦争回避、緊張緩和、国際平和に貢献することの重要性を分かり切ったうえで、日本の自公政権が「日米同盟機軸」という思考抜きの前提命題に軸足を置き、アメリカのシナリオ通りに戦争のお先棒を担ごうとしていることへの不信を投げかけておられる。ご指摘のとおりですね。ではどうするか、【回答2】を参照してください。
【質問6】;経済力世界一となった中国。一方で少子化や若者の働く口がなく夢が持てない…などの報道も目を惹きます。一番危惧を持つのは、モンゴル(少数民族)政策、海洋進出、一帯一路政策など、非民主主義的、覇権主義的な動向であり、受け入れ難い思いでいる。このような疑問も、メディアの一方的論調に左右されていることになるのだろうか?
【回答6】;この質問は遠慮されて質疑応答終了後に頂いたものです。中国の情況をよく理解されたうえでも、なお筆者を含め多くの方が危惧されている問題だと思います。次のように考えています。
⓵ 中国の世界における存在が巨大化していくにつれて、中国の国際対応が次第に国内的基準(「上から目線の超越的指導」)だけでは通用しなくなり、国際的な場でも認知される新たな基準を自ら開発し、獲得していく新しい時代を迎えています。まだその過渡期にありますが、中国政府が2023年2月24日発表した「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」は、冒頭第1項目で「各国の主権の尊重。国連憲章の趣旨と原則を含む、広く認められた国際法は厳格に遵守されるべきであり、各国の主権、独立、及び領土的一体性はいずれも適切に保障されるべきである」と明記しています。これは中国の国際対応についての基本的原則となるものです。
⓶ とはいえ、米国は「インド太平洋戦略」に基づいて「台湾有事」を軸に、同盟国を巻き込んで安全保障・軍事展開、経済関係の全局に対中包囲網(デカップリング)を徹底していきますから、中国は対抗を強化したり、国際外交を強めて挑発を回避したりと、揺れ動いていくことでしょう。
この⓵⓶の両側面を見すえて、ひとつひとつの問題を腑分けしながら対応を考察することが大切です。メディアは全ての問題を中国の強面(大国主義、覇権主義)と一括して描き、論じますから、慎重かつ丁寧な作業が欠かせないのです。
*モンゴル・新疆・チベットなど少数民族政策
これは今や国際問題化していますが、基本的には国内問題です。中華人民共和国の伝統的な少数民族政策は少数民族の自治と「教育・言語・宗教」の尊重と発展を保証する優れた内容を持つものですが、習近平政権の下で「中華民族という共同体意識の定着」を名目に、改変されようとしています(「イスラム教の中国化」、「少数民族の独自語を排除した共通語(漢語)教育の普及」)。習近平さんの考え方は、毛沢東が繰り返し警告した「大漢族主義」の一変種だと、筆者は考えています。もしこれが放置されるなら、中国は「全崩壊」(故加々美光行氏の言葉)に至りかねず、是正されなければならないと、思います。これについては、拙稿「中国の現代化達成の最適ルートは平和と安定にあり」上・下『平和運動』2021年10・11月号参照。
*「一帯一路」政策
習近平政権の登場と共に登場したスケールの大きな国際協力事業ですね。この政策の強みは、新興国や後発国における経済発展のベースともいうべきインフラ建設投資への膨大な需要があるにもかかわらず、世界銀行、国際通貨基金が機能不全状態にあるのに対して、中国が新たな国際金融機関AIIA(アジア・インフラ投資)銀行を設立し、インフラ建設投資に直接乗り出したことです。すでに膨大なインフラ建設事業が進行中ですが、二国間協力方式が中心となっているため、投資協定や返済方式、協力事業の進め方などをめぐって摩擦や軋轢も生じており、数例とはいえ事業中止や債務問題表面化のケースも出ています。こうした問題は経済協力事業にはありがちなことです。しかし、米国主導のデカップリングが進行する中で、一帯一路協力を「債務の罠」とあげつらい、悪意の「政治問題化」に利用する動きもあります。一帯一路協力事業の対象国は中国が重視する「グローバルサウス」諸国であることから、地政学的な「影響力の増大」の意図という側面だけを誇大視、強調する動きです。G7はじめ先進諸国は、中国が当初から世界に呼びかけている、「一帯一路」協力を国際的公共事業として共同で進めようとする提案をまともに検討しようともしません。「一帯一路」問題は、調査と分析にもとづく批判や改善提案はありえても、性質の異なる諸問題とゴッタ煮にして論じることは控えるべきでしょう。
拙稿「中国の『一帯一路』構想とその推進」『研究中国』No.8(通巻128号)2019年4月もご参考に。
*海洋進出
この問題は確かに多岐にわたり、複雑な要素が絡んでいます。
南シナ海における近接諸国の排他的海域(EEZ)内における領有権紛争; 海上交通の要衝で、好漁場でもある南シナ海は、石油ガス資源が有望視されだした70年代から周辺国が領有権の主張を強めてきました。小島や岩礁などを埋め立てたり、港湾・滑走路・石油試掘施設・生活空間等を設置することによる「実効支配の実績」拡大が紛争を引き起こしているのです。その中でも、「南シナ海の9割に管轄権が及ぶ」と主張し、軍事力、経済力で突出している中国に対して「覇権主義」だと批判する声が強まっています。事態を憂慮する東南アジア諸国連合(ASEAN)と中国は、02年に「領有権問題は平和的に解決する」との「行動宣言」に署名していますが、ASEANは引き続きこれに法的拘束力を持たせるため、中国に対して南シナ海に関する「行動規範」を早期に締結するよう働きかけています。
尖閣・東シナ海問題; 尖閣諸島の領有権については、やはり1960年代末に東シナ海の大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性があることが判明し、注目されてきましたが、72年の日中国交回復の際、問題の処理を棚上げしたことがよく知られています。日中両国は公式には、それぞれ理由を挙げて領有権を主張しています。日本側は「中国が領有権を主張しているという認識は持つが、領土問題が存在するという認識はない」、という立場です。中国側は「日本は中国が違う認識を持っていると認識したのであれば、領土問題の存在を認めたことになる」、という立場です。これでは平行線をたどるだけなので、両国政府は日中関係の改善に向けた話し合いを経て、2014年11月に次のような意見の一致を見ました。「双方は、尖閣諸島等東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じて、情勢の悪化を防ぐとともに、危機管理メカニズムを構築し、不測の事態の発生を回避する」。
台湾海峡・東シナ海; ここでは成立期の中華人民共和国と台湾国民党政権との間での台湾海峡をめぐる第一次危機(1954 - 1955年)、第二次危機(1958年)および国民党独裁終了後の台湾の進路に関わる第三次危機(1995、96年)など歴史的過程での問題はとりあえず省き、2022年米国下院議長ペロシが台湾独立論テコ入れのため訪台した直後からの台湾周辺海域問題を考えます。8月、ペロシ帰国直後からの中国側大軍事演習はそれまでの台湾海峡、南シナ海に加えて東シナ海から台湾南部海域を含む台湾包囲型の大演習に転じました。ペロシ訪台後、米国議会で「台湾政策法案」(台湾を同盟国として外交特権を付与し、従来のレベルを超えて攻撃的兵器も供給する「一つの中国論放棄」の法案で、今はまだ可決されていない)という「米国シナリオによる台湾有事」の動きが強まる中で、中国は沖縄における米日共同軍事演習への対抗、中国海警局艦船の尖閣諸島長時間航行強化、南シナ海での人民解放軍海・空軍の演習強化など全域での警戒行動を整えています。
以上、質問6のうち、「少数民族問題」での危惧は、筆者は質問された方に全面的に共感する立場を示しました。「一帯一路」については、冷静に観察すれば 「危惧<評価」 という判断を示しております。「海洋進出」は南シナ海問題でのASEANと中国との、尖閣問題での日本と中国との「対話と協議」およびそれにもとづく「合意と取り決め」の積み重ねによって、双方が歩み寄りながら問題解決に近づく可能性が示されていることに、注目しております。ただこのような方向も「台湾海峡・東シナ海」に見る、アメリカの「アジア回帰」、「インド太平洋戦略」のように「対話と協議」の道を強引に塞いでしまい、「対中包囲網」で窒息させようとする米国流一辺倒では、国際協調は遠退くばかりではないか、という逆の危惧を示しました。講演ではこの最後に述べた視点を基調にしてお話いたしました。
山本恒人